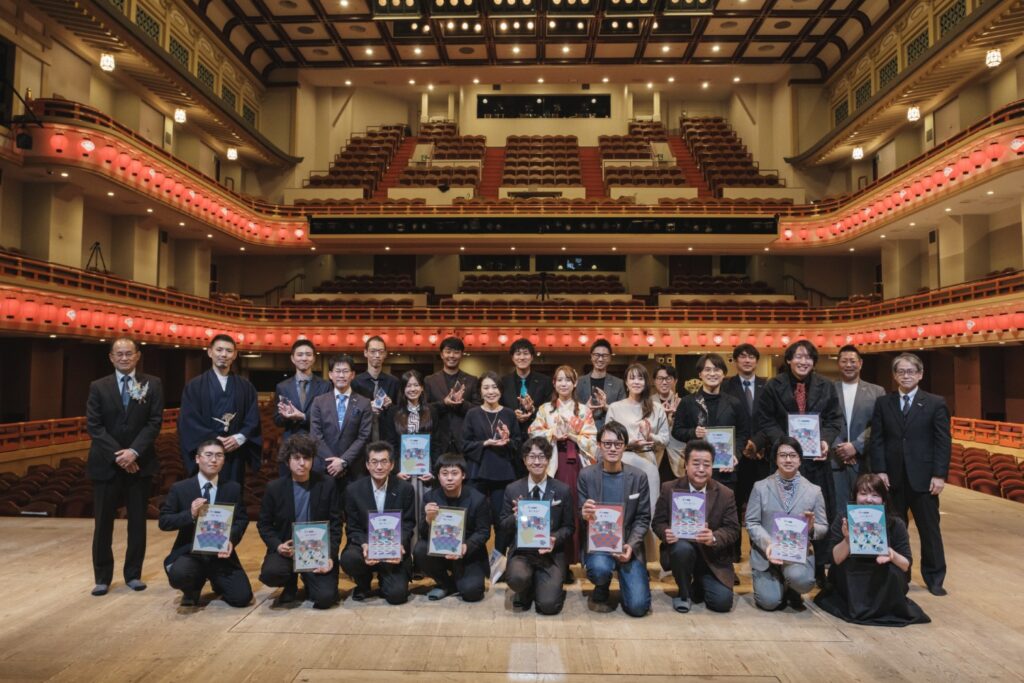SAWAMURA PRESS

時間外労働の上限規制や週休二日制、団塊の世代の引退による人手不足。変革期を迎える建設業界では今、業務のバックオフィス化が急速に進んでいます。
今回、業界全体が直面しているさまざまな課題と日々向き合う業務改革推進課の藤森さんに、SAWAMURAの進める働き方改革について伺ってきました。
PROFILE
コーポレート統括部 業務改革推進課
藤森さん

高島市出身で2013年に新卒で入社。法人の工事を請け負う部署で現場監督を務めた後、2021年から現場の仕事を内部からサポートする業務に従事。現在は現場での経験を活かして、業務の電子化や社員のスキルアップなど、SAWAMURAの働き方改革を進めている。
現場監督の仕事は、昔から長時間労働が問題になっていました。

ー現在所属している業務改革推進課の業務内容を教えてください。
藤森:もともと現場監督をオフィスからサポートする工事サポート課で仕事をしていました。そして昨期から組織体制が変わり、今はより会社全体のサポートをする仕事をしています。
ー働き方をよりよく改善するお仕事なんですね。
藤森:そうですね。特に現場監督の仕事は、昔から長時間労働が問題になっていました。業界全体の働き方が変わる今、現場だけで仕事を完結するやり方は時代に合いません。だからSAWAMURAではバックオフィスを充実させて、社員みんなが働きやすい仕組みづくりをしています。
ーちなみに藤森さんは現場監督の経験もあるそうですね。当時はどれくらい忙しかったのですか?
藤森:もちろん昔の話ですけど、一番キツイ時だと、ちょっとここでは言えないくらいの残業と休日出勤でしたね。ちょうど子供が産まれた年で。半年間くらいは懐いてもらえなかったです(笑)。
ー大変でしたね。そもそも現場の残業の原因は?
藤森:現場監督の仕事には、工事の品質や安全を保つために必要な書類作成が多いんです。例えば工事写真というものがあります。仕様書通りに施工しているかを記録するために、工事の工程を細かく写真に残す仕事です。SAWAMURAの建築現場の規模だと、ひとつの現場でだいたい5000枚くらい。大きな会社の現場だと何万枚にもなります。そして撮った写真に説明を付けて、仕様書と間違いありませんという証拠の書類をつくります。
ほかにも安全書類というものもあります。現場の作業は協力業社にお願いするのですが、その作業員がちゃんとした保険に入っているか、資格を持っているかなどを全部確認する書類です。必要な書類をすべて出してもらって、作業員の人数分確認しなければならない。こういった事務作業が、実はすごく多いんですよ。
ーそれを現場だけで対応するのは非常に負担ですね。
藤森:今より社員数の少ない時代は、ひとりで複数の現場を持つのが当たり前。どうしても書類作成が後回しになってしまって。定時以降からの作業が当たり前になり、残業がどんどん増えていくという流れでした。
バックオフィスの充実で、現場の残業時間を大きく削減できている。
ー現場監督が行っていた書類作成は現在どうなっているんですか?
藤森:昨年10月に、現場で撮影した写真をすぐに社内のPCへ共有できるシステムを導入しました。現場ごとに対応していた資料作成は、今では社内で対応しています。
ー一気に負担が減りましたね。他の作業はどうですか?
藤森:安全書類の電子化は、3年前くらいから会社全体で実施しています。今、現場では最終チェック程度しか安全書類にさわっていません。ただ協力業社の中にはパソコン作業が苦手な方もいて、書類をちゃんと提出してくれないところもある。そこで私たちが協力業者へ電子化のお願いすると同時に、運用サポートもしています。
ーちなみに今は何社くらいを管理しているんですか。
藤森:今、登録されているのは約240社です。これが結構大変なんですよ。

ー電子化してもまだ大変なんですか?
藤森:協力業者に「電子化します」と言った際、問い合わせの窓口を当社にしてしまって。わからないことがあった時、システム会社ではなく、こっちに電話やメールが届くんです(笑)。今ではパソコン画面を見なくても、どう操作したら解決できるかわかるので、出先からでも指示を出せるほど詳しくなっています(笑)。
ーバックオフィスの充実で、現場の残業時間に変化は?
藤森:去年の残業時間を計算してみたんです。オフィスや工場など法人向けの現場だけですが、去年の平均で月15時間。自分でもビックリしました。私が現場にいた時とは社員数が大きく違いますが、バックオフィスの充実も効果があったと思います。現場の社員に聞いてみても、ちゃんと帰れていると聞くのでサポートする立場からするとうれしいですね。
現場の仕事を巻き取ることで、
現場で学べる知識が少なくなったという面もある。

ー現場の仕事が電子化したことで、見えた課題はありますか?
藤森:バックオフィスが充実することで、若手の学べる知識が少なくなったという面はあります。同じような話は他社からも聞くので。現場の上司たちからも、社内で巻き取りすぎるなと言われたこともあるくらいです。
でもそれでは現場をサポートする部署として役割を果たせません。減らせる業務は減らして、そのうえでもっと専門的な業務を担当してもらえるように、仕事のやり方を変えていこうと取り組んでいます。
ー専門的な業務というと?
藤森:簡単にいうと、これまでベテランがやっていた業務ですね。例えば施工図を描くとか。施工図というのは、設計図をもとにして作成する作業図面なんです。資料作成の時間を削減できた分、より専門的な業務に早く携わるほうが、現場監督としての成長も早いんじゃないかと思っています。
ー藤森さんの感じる、現場でしか学べないことはありますか?
藤森:私の初めての現場は、鉄筋コンクリート構造のマンション。大工さんたちの後ろについて回り、現場の仕事を覚えていきました。現場では業者さん同士の本気の喧嘩を間近で見ることも。でもちゃんと聞いていると、実はお互い言っていることは真っ当なんです。
だいたいの原因は現場監督側の問題が多い気がします。そこで「こういう工程を組めていないから、喧嘩が起きるんだ」と気づくわけです。そうやって現場での経験を重ねることで、仕事が円滑に進む業社とのコミュニケーションを磨いていく。これがとても大切だと感じました。そういうことは教科書には書いてないですからね(笑)。
変革期を迎えた建設業界。
会社としても資格を持つ技術者を増やしていきたい。
ー資格取得のサポートにも力を入れているそうですね。
藤森:はい。今年から取り組んでいます。建設業界は資格を持っていないとできない業務もたくさんあります。人材育成も働き方改革の手段と捉え、社員の資格取得を会社でバックアップしています。いろんな資格がありますが、現場の仕事でよくいわれるのは、施工管理技士という国家資格ですかね。
実は施工管理技士の資格は、団塊の世代が引退し出した影響からか、令和6年度から法改正が行われました。受験資格の見直しで、必要な実務経験の年数が大幅に短縮されるなど、広く受け入れられるようになりました。
ーそれだけ業界の人手不足が深刻なんですね。
藤森:建設業界は今、大きな変革期を迎えています。そういう状況なので、会社としても資格を持った技術者を増やして仕事の入口を広げたいという狙いもあります。
ー資格取得のために、具体的にはどんなことを?
藤森:資格取得までには費用もそれなりにかかります。そこで資格スクールと連携して、希望者にテキストの配布をしたり業務時間中に模試を実施するなど、資格取得にチャレンジしやすい環境を整えています。ほかにも1級建築士という国家資格については、スクール費用が高額なため、会社から貸し出す制度もあります。
バックオフィスを現場の人材育成の場に。

ー業務改革推進課がこれから目指すことは?
藤森:今は上司と、採用について話し合っています。業務改革推進課として、高卒の社員を採用していけないかと。実際、大学で建築を専攻していた方でも、施工管理の知識や技術があるわけではないので、即戦力とはならないんです。
それなら未経験の高卒の方でもまずは業務改革推進課に来てもらい、資料作成などの業務を先輩がいる環境の中で覚えてもらう。そして5年程度を目処に、現場の施工管理へとステップアップしていく。人材を養成していける体制を整えていきたいですね。そうやって建築・土木の現場を任せられる人数を増やしていきたいと思っています。
ー現場のサポートだけではなく、人材育成できる課も目指されているのですね。今後も期待しています。今日はありがとうございました。
今回は藤森さんへのインタビューを通して、業務改善に向けた現場の工夫や想いをご紹介しました。
SAWAMURAにはこうした“前向きな変化”があちこちで生まれています。
これからも、会社を変えるきっかけとなる人や取り組みを紹介していきますのでどうぞお楽しみに!
この記事を書いた人
 |
福馬俊太郎 滋賀県高島市在住。フリーの編集・ライターとして活動中。SAWAMURA社内報の取材・執筆にも携わる。 |
Interview&Text:福馬俊太郎/Edit:SAWAMURA PRESS編集部