SAWAMURA PRESS
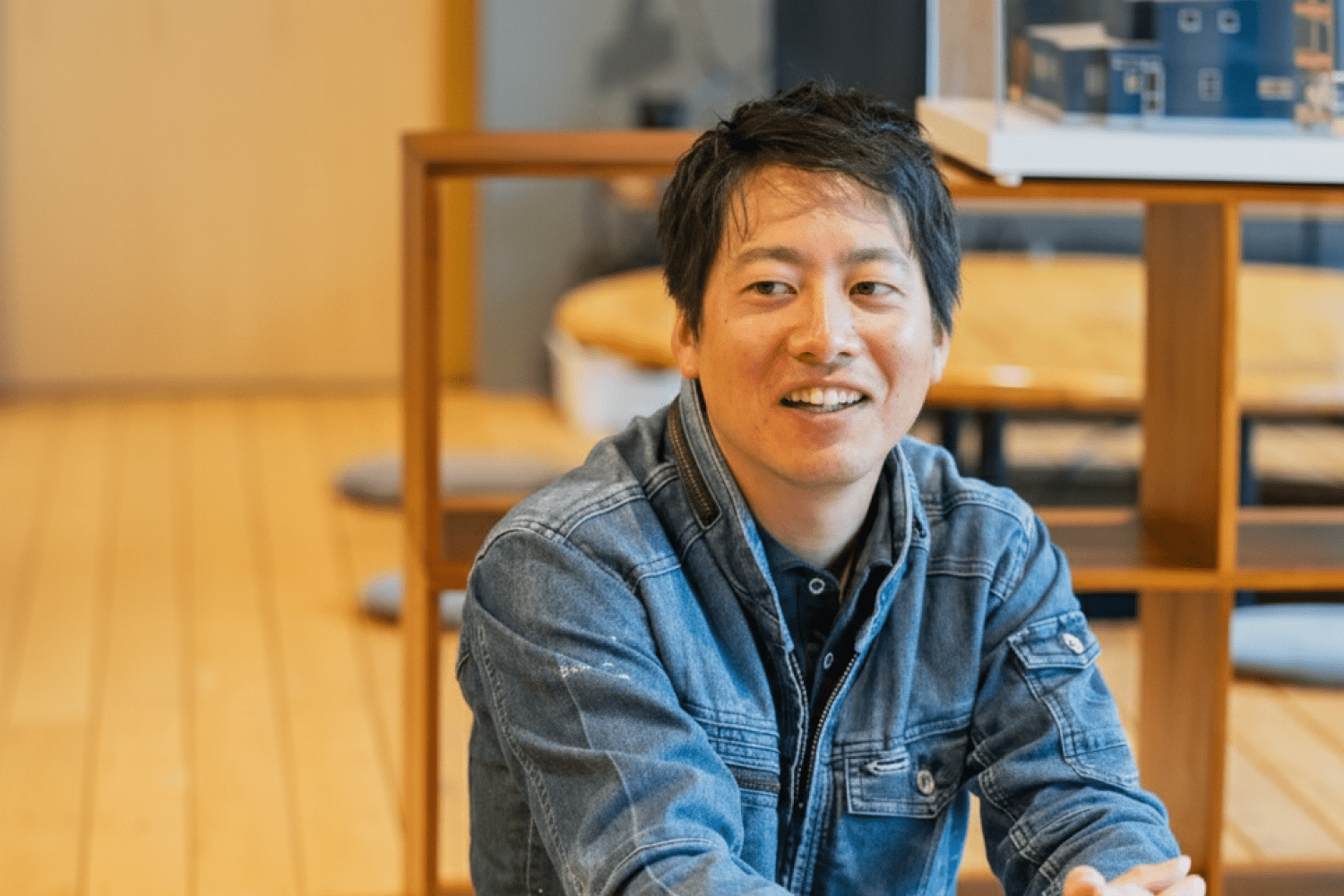
キャリア採用にも積極的に取り組み、多様な人材と能力が集まってきているSAWAMURA。
さまざまなバックグランドを持つ彼らが、なぜSAWAMURAを選んだのか。そしてどんなビジョンを持っているのか。キャリア人材にスポットを当て、一人ひとりの仕事観をお伝えしていくシリーズ。第3回のゲストは施工管理として建築の現場で活躍する清水さんです。
GUEST PROFILE
工事グループ 工事Ⅰ課
清水さん

1991年生まれ、滋賀県出身。大阪工業大学工学部建築学科卒業。新卒で滋賀県の建設会社に入社。以来、施工管理として20代を過ごす。2021年SAWAMURAに入社
設計で飯を食っていくのは無理。そう痛感して現場の道へ。

編集部:今日はよろしくお願いします。さっそくですが、SAWAMURAに入社する前のことを教えてください。
清水:前職は県内の建設会社で施工管理の仕事をしていました。そこで工場、店舗、公共施設、マンションなど幅広く手掛けていましたね。
編集部:その会社には新卒で入ったそうですが、そもそもどうして施工管理を目指そうとされたんですか?
清水:施工管理を目指すきっかけは大学時代。建築学科に入ったこともあり、当時は設計士を目指していたんです。でも1年目で挫折しました。センスある人や絵が上手い人を間近に見て、設計で飯を食っていくのは無理。そう痛感して現場に切り替えました。
編集部:確かに建築学科って、設計士を目指す人が多そうです。
清水:そうなんです。それで施工管理をするなら大手ゼネコンを目指そうと就活をしていました。でも行きたかったところに行けなくて。他のゼネコンに妥協するくらいなら、地元の滋賀で働きたいなという思いになり、父も建築会社で施工管理の仕事をしていたので相談してみたんです。「今、一番勢いのある会社はどこ?」って。ギラギラした感じが聞き方に出てるけど(笑)。で、教えてもらったのが前職の会社です。
編集部:確かにギラギラしてますね(笑)。清水さんは、やさしくクールなイメージだったので意外です。
清水:今でも現場ではスイッチが入るというか。管理することが仕事なので、伝えたいことをしっかり伝えるのも大切な仕事だと思っています。
忙しい日々の中、家族との時間を第一に考え転職。
編集部:それでは話題を転職活動に移します。清水さんは、同じ県内で同業種であるSAWAMURAに転職しました。どんなきっかけでしたか?
清水:新卒で入社して20代をまるっと前の会社で過ごし、仕事そのものは楽しかったし、不満はありませんでした。ただ正直休みが少なく、少しずつ体力的にキツくなってきた。ちょうど結婚して、子供も産まれ、30歳というタイミング…。このままここで働き続けるか、それとも動くか。ぼんやり考えていたんです。でも忙しいので転職活動なんてできるわけもなく。転職サイトやスカウトサービスにだけ登録していて、そこで声をかけてもらったのがSAWAMURA。とりあえず一回話だけでも聞いてみようって感じでした。 編集部:転職する上で大切にしたことは?
編集部:転職する上で大切にしたことは?
清水:今よりも家族との時間を大切にできる。最初はそれだけだったかな。それ以外のことはあまり考えていませんでした(笑)。でも澤村社長とお話して、今まで見てきた社長のイメージがガラッと変わった。なんていうか、建設会社っぽくないところにすごく魅力を感じました。振り返るとそれが一番の決め手になったように思います。それと新卒もキャリアも積極的に採用して、若いスタッフがたくさん活躍している。この先、会社がさらに大きくなりそうな勢いも感じましたね。
編集部:確かに建設会社の社長っぽくないとはよく聞きますね。ちなみに前職と同じ滋賀県内に転職というのは当初から決めていましたか?
清水:新卒で地元に戻ってきたので、ここからわざわざ県外に出るという発想はなかった。それこそ県外に出るのであれば、大手ゼネコンの総合職くらいかなと。けど、小さな子供を妻に任せて地方を転々とする暮らしは嫌で。妻も県内にいたいと言っていたので家族を第一に考えました。
僕らは現場の人間なので、技術で会社の底上げをしたい。
編集部:同業種の会社に転職して、前職との違いはどこに感じますか?
清水:家族との時間は前よりもつくれるようになり、体力的にも気持ち的にもすごく楽になったかな。あとは、どの会社も採用する時って「自分の会社は人を大事にしている」って言いますよね(笑)。でも実際どうかって、入ってみないとわかんないじゃないですか。SAWAMURAは「社員を大事にしたい!」というのを、入社してからもすごく感じますね。
編集部:キャリア入社の清水さんからの言葉は重みを感じます。ちなみに、今はどんな仕事をされていますか?
清水:建築の施工管理として、より良い建築物をつくるために工程・原価・施工などの管理が主な仕事です。下請け工事もあるので、施工方法などの提案・見積もりなどもしています。やっている事自体は前職と大きな違いはないかな。
編集部:前職とほぼ仕事内容は同じで、働く場所もほぼ現場。会社とのつながりは感じにくいと思うけど、今、モチベーション高く取り組めていることは?
清水:う〜ん。僕らは現場の人間なので、技術的なところで会社の底上げをしたいですね。前の会社で働いていた時、正直SAWAMURAのことは知りませんでした。それは学生とか一般の人が知らないのとはちょっと意味が違う。だから、もっと同業者からも認めてもらえるようになりたいですね。

編集部:なるほど。現場のリアルな意見ですね。新卒向けのナビサイトの閲覧数ランキング等では、県内の建設業ではずっと上位。採用人数も他社と比べて多い方なので、県内の建設業界では知名度があると思っていました。
清水:僕がSAWAMURAのことを知らなかった理由は、公共工事の入札案件であまり見かけなかったのが大きいのかもしれない。規模の大きな仕事を受注していると、やっぱり同業者の目にとまりやすい。
編集部:今、会社としては設計・施工の一貫体制が活かせる民間の案件が中心なので 、なかなか同業者には伝わりにくい部分があるかもしれません。これから入札案件に力を入れる動きもあるのでしょうか?
清水:経営層も入札案件は検討しているみたいです。 ただこれから入札に参加するためには、どうしても価格を抑える必要がある。今の時代、価格を抑えるって結構難しいけど、そこは前職の経験を活かせる部分もあるので、よく相談を受けています。
編集部:SAWAMURAのブランド価値を守りつつ、入札にもチャレンジする。やりがいがありそうですね。
育休を取りやすくするためにも、やっぱり技術の底上げが必須。
編集部:さきほど転職してプライベートな時間が増えたと話されていましたが、休みの日の過ごし方は?
清水:3歳と4歳の子供がいるので、自分の時間というのはなく…。公園に行ったり、買い物行ったり、休みの日は子供中心。最近は福井県にある絵本作品をモチーフにした公園に行きました。逆に自分一人だと何をしていいのかわからないです(笑)。子供がいるから、充実している気がする。

編集部:ちなみに育休は取得しましたか? 社内でも取得する男性社員が増えていますが、現場で働く人たちはどう考えているのか気になっています。
清水:僕は取得してないけど、今後部下や後輩が取得したいと出てくることも十分理解しているつもりです。
編集部:他の課と比べて取得する時の大きな壁は、現場の調整ですか?
清水:そう。やっぱり施工管理は、現場の責任者なので。誰かがパッとヘルプに行っても、どこまで段取りしているかがわかりにくく現場を納められない。SAWAMURAでは今、複数人で管理して一人現場をできるだけなくす動きがあるけど、この体制が浸透すれば現場の社員も育休を取得しやすくなると思う。
そのためには、さっきも言ったけど技術の底上げが必須。現状、若手だけで現場をまわすことは難しい。技術力を上げて、現場をまわせる人材を増やし、複数人で管理する。これが今の理想ですね。
より難しい、高い技術力を求められる仕事をしたい。
編集部:そういえば先日「SAWAMURA VISION」がありましたね。清水さんは工事グループを代表したVISIONリーダーでしたが、やってみてどうでしたか?
 全社員が参加するワークショップを軸とした「SAWAMURA VISION」
全社員が参加するワークショップを軸とした「SAWAMURA VISION」
※編集部注「VISIONリーダー」
社員一人ひとりの思い描く未来像(VISION)を形にし、共有する社員総会「SAWAMURA VISION」において、企画運営を担当するメンバー。各部門から任命を受け、当日だけでなく、チームでの対話を支援していく役割。
清水:普段は現場が中心なので、会社の一員であることを実感することが少ないんだけど。VISIONリーダーをやってみて、社員がどんな想いで働いているのかを認識できたすごくいい機会だった。それこそ、SAWAMURAに来てからブランディングの重要性をすごく感じていて。建設業界の中でも、時代にあった取り組みをしていると感じます。
編集部:現場の魅力をブランディングに活かして、SAWAMURAの魅力をもっと発信していきたいですね。では最後に清水さんが今描いているビジョンを教えてください。
清水:僕は技術屋なので、より高い技術力を求められる仕事がしたい。そしてSAWAMURAを同業種の会社から技術力で一目置かれる組織にしていきたいですね。
今は新卒もキャリアも人をたくさん採用している会社として他社からも知られていて、そこに注目が集まりがち。「で、次は?」となったら、建設会社として注目されることが大切だと感じています。やっぱり会社がキャリア組に求めるのは、そういう客観的な視点を活かした組織のアップグレードだと思うので。そこにチャレンジしていきたいですね。
編集部:技術屋は技術で勝負したい。いいですね。今日はありがとうございました。
この記事を書いた人
 |
福馬俊太郎 滋賀県高島市在住。フリーの編集・ライターとして活動中。SAWAMURA社内報の取材・執筆にも携わる。 |
Interview&Edit:SAWAMURA PRESS編集部/Text:福馬俊太郎





















