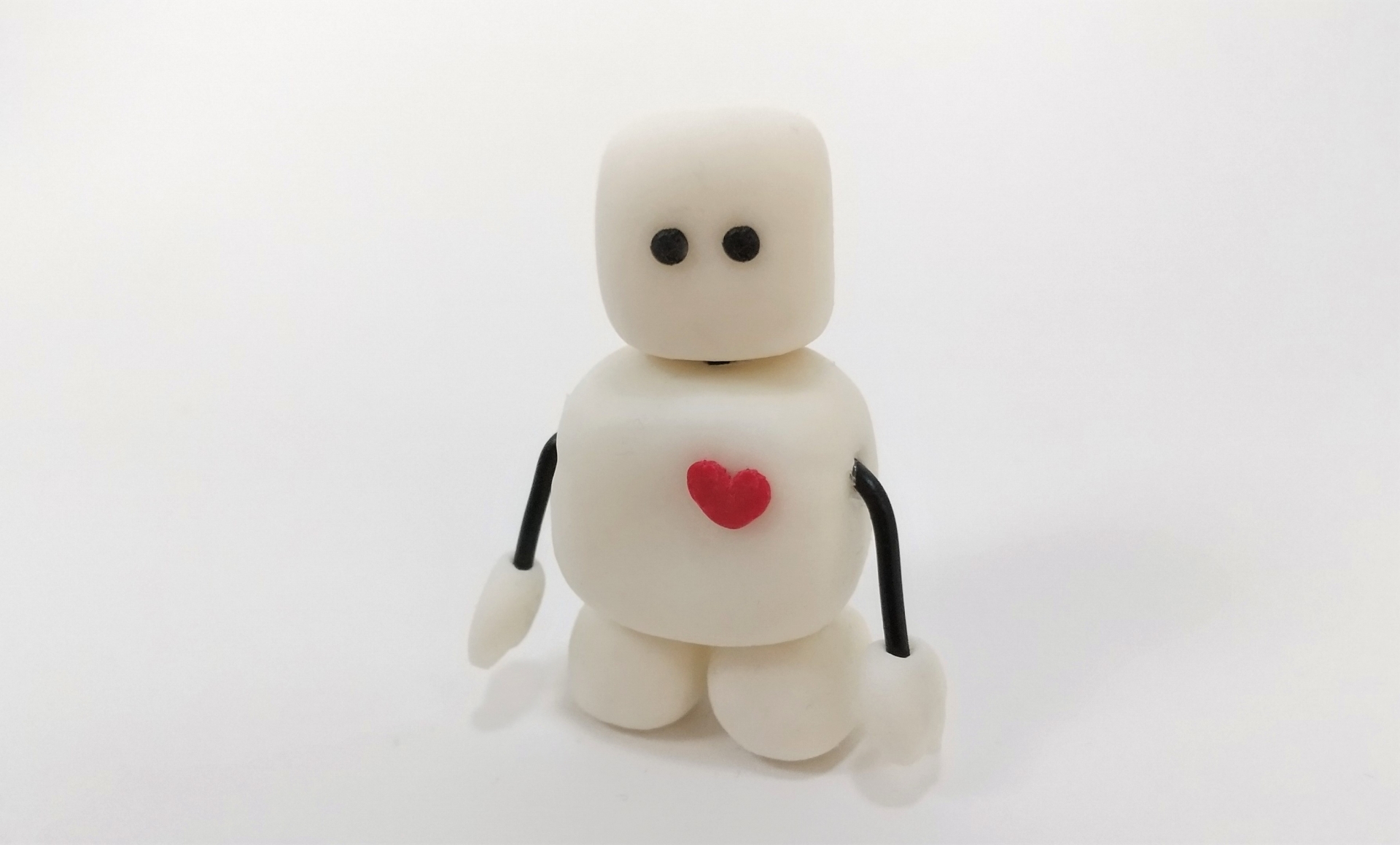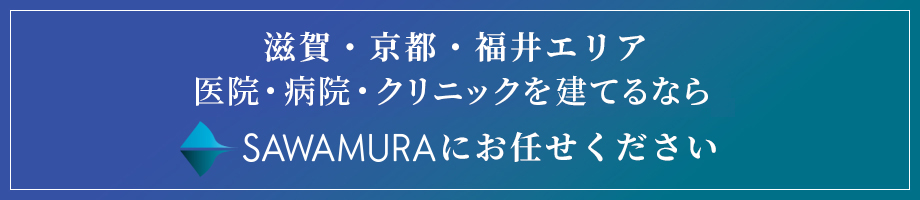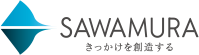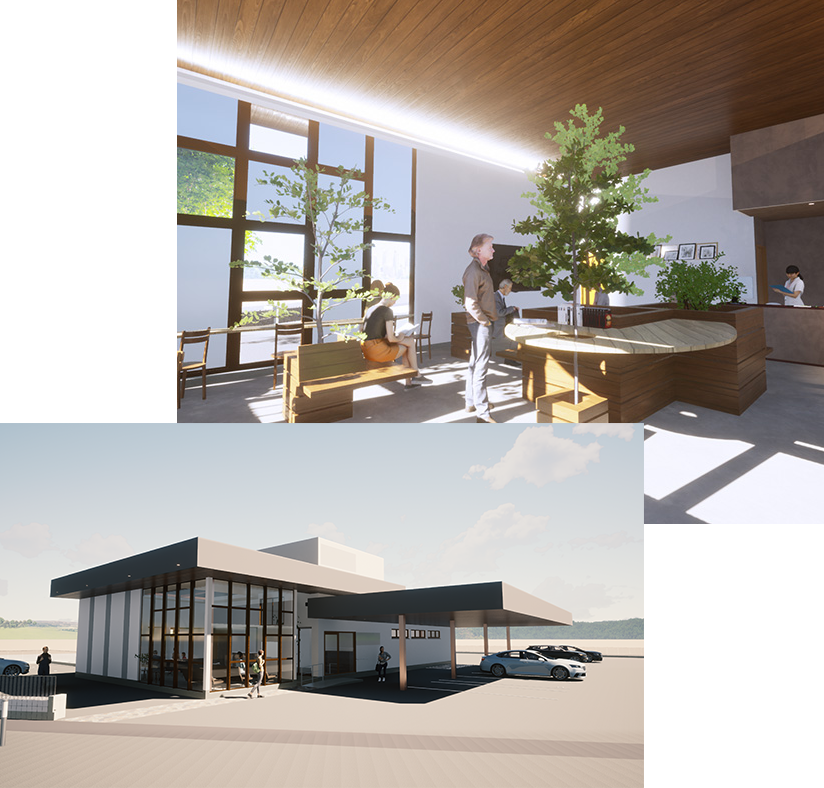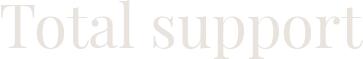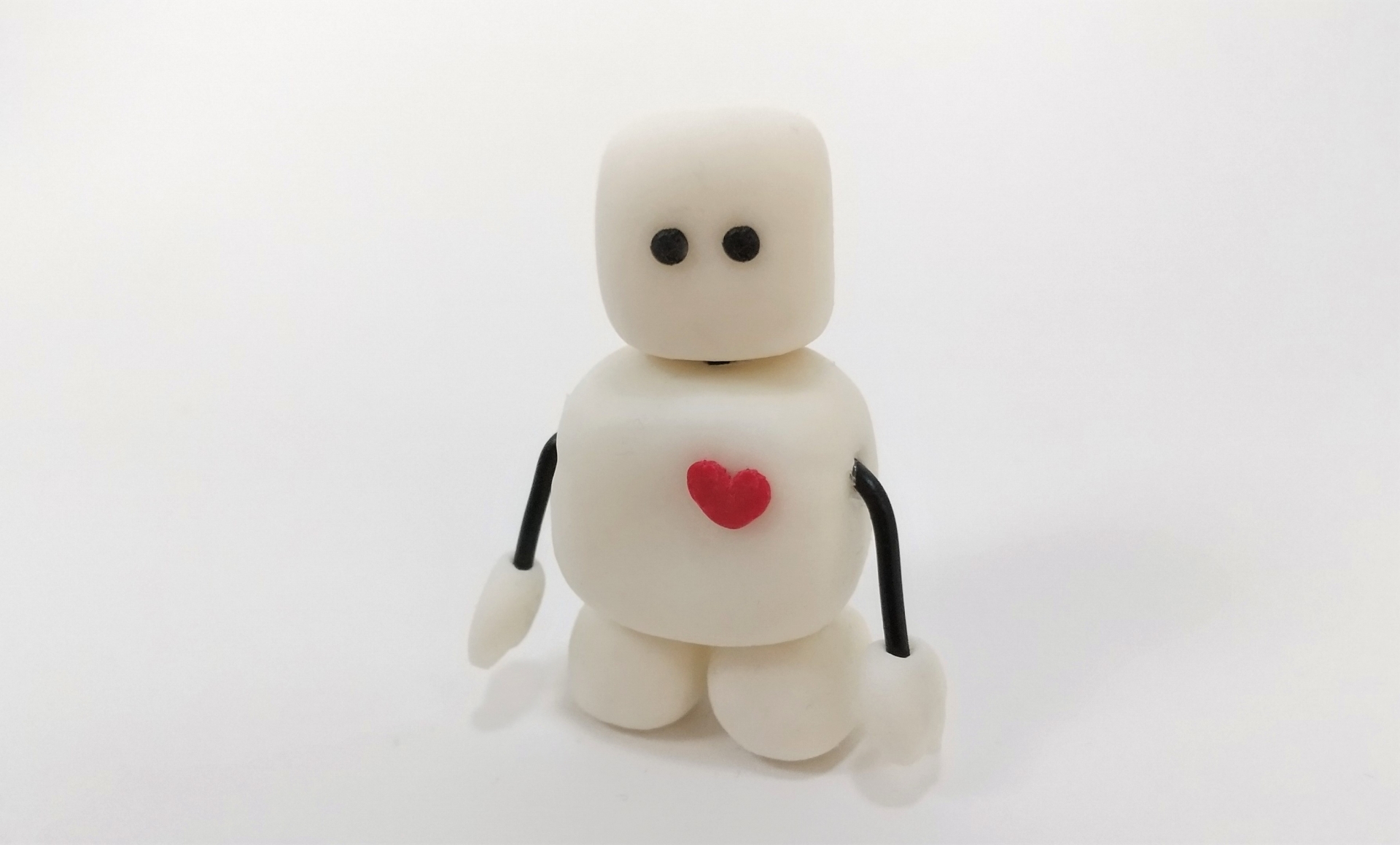
最終更新日:2022年12月28日
介護の現場では、介護ロボットの導入が開始しています。ロボットに介護を任せても安全なのか、実際に役立つのか疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、介護ロボットの特徴や実用性、導入のメリット、安全性などについて詳しく解説します。介護の効率化、介護ロボットの導入を検討中の方はご覧ください。
介護ロボットとは
介護ロボットとは、生活面の介護を介護者の代わりに行うロボットです。介護者の負担軽減を目的として開発され、介護施設への導入が開始しています。ただし、介護ロボットに全ての介護を任せられるわけではないため、「できること・できないこと」を理解したうえで導入を検討する必要があります。
介護ロボットが注目されている背景
2013年6月に、政府は介護ロボットの開発および導入促進に取り組むことを発表し、「ロボット技術の介護利用における重点分野」を策定しました。ロボットメーカーへの支援はもちろん、介護ロボットを導入する施設への補助金の支給、実際にロボットを使用した人の声がメーカーへ届く仕組み作りなど、さまざまな方法で介護ロボットの開発・導入支援を行っています。
政府が介護ロボットの開発・導入支援に力を入れている背景には、少子高齢化社会の到来があります。介護を行う若手に対して、介護される高齢者が多い状況のため、このまま少子高齢化が続くといずれは介護の人手不足が生じるでしょう。
介護ロボットは、少子高齢化による介護の現場への影響を軽減する方法として、大きな注目を集めています。
介護ロボットの普及状況
介護ロボットの開発は進んでいるものの、普及率は高くありません。これには、1種類の介護ロボットでは1つの介護しかサポートできないことが関係しています。1つの作業を任せるだけでは、介護者の負担を大きくは軽減できません。食事や入浴、排せつ、立ち上がりの介助、歩行の介助など、介護者が行うべきことはさまざまです。
これら全てを介護ロボットに任せるには、複数のロボットを導入する必要があります。今後、より高機能で高性能な介護ロボットが開発されれば、普及率は上がるのではないでしょうか。
介護ロボットの安全性
介護ロボットの安全性は現時点では不明です。ただ、人と接する以上は安全性を第一に考えて設計する必要があるため、安全性の向上やリスクの把握および解消については、ロボットメーカーが大きな力を注いでいます。
また、市場に出るまでに数々の安全性試験が行われるため、安心して使用できると言えるでしょう。
介護ロボットを導入するメリット
介護ロボットを導入すると、介護者の心身の負担を軽減できます。大人の要介護者を支えて歩いたりベッドから起こしたりする際は、全身の筋力を使います。このような日々を過ごすことで心身の負担が増加し、退職してしまうケースも少なくありません。
介護人材が貴重な現代においては、1人ひとりの介護者の負担を軽減することが重要と考えられています。また、他人に介護されることに恥ずかしさや申し訳なさを感じる人に対し、介護ロボットによる介護を提供することで、精神的なストレスを和らげられる可能性もあります。
介護ロボットを導入するデメリット
介護ロボットのデメリットは、導入コストが高いことです。また、スペースを取るため、施設の面積によっては導入が難しいでしょう。また、導入したものの操作が難しく、使いこなすまでに時間がかかるケースもあります。
介護ロボットの種類
介護のさまざまな場面で活躍する介護ロボットが開発されています。介護ロボットの種類について詳しくみていきましょう。
移乗介助機器
移乗介助機器には、介護者のパワーアシスト機能を持つ介護ロボットで、「装着型」と「非装着型」があります。いずれも介護者が要介護者を抱き上げるのをサポートしたりする際に、身体への負担を軽減します。
移動支援機器
移動支援機器とは、要介護者が自力で歩くのを支援する介護ロボットです。外出する際に
使用する「屋外型」と屋内でトイレやベッドへの往復などに使用する「屋内型」があります。
排泄支援機器
排泄支援機器は、居室に設置することでトイレに移動することなく排せつができるようになる介護ロボットです。排泄物や室外に流したり密封したりして、臭いが室内に拡散するのを防ぎます。
入浴支援機器
入浴支援機器は、浴槽に入ったり出たりする動作を補助する介護ロボットです。設置に特別な工事は不要なため、家庭にも導入しやすいでしょう。
まとめ
介護ロボットは、介護者の心身の負担や介護される側の恥ずかしさや申し訳なさなどを軽減するロボットです。政府が介護ロボットの開発・導入促進に力を入れており、大きな注目を集めています。介護ロボットがさらなる進化をして実用性や安全性が高いレベルになった際は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。